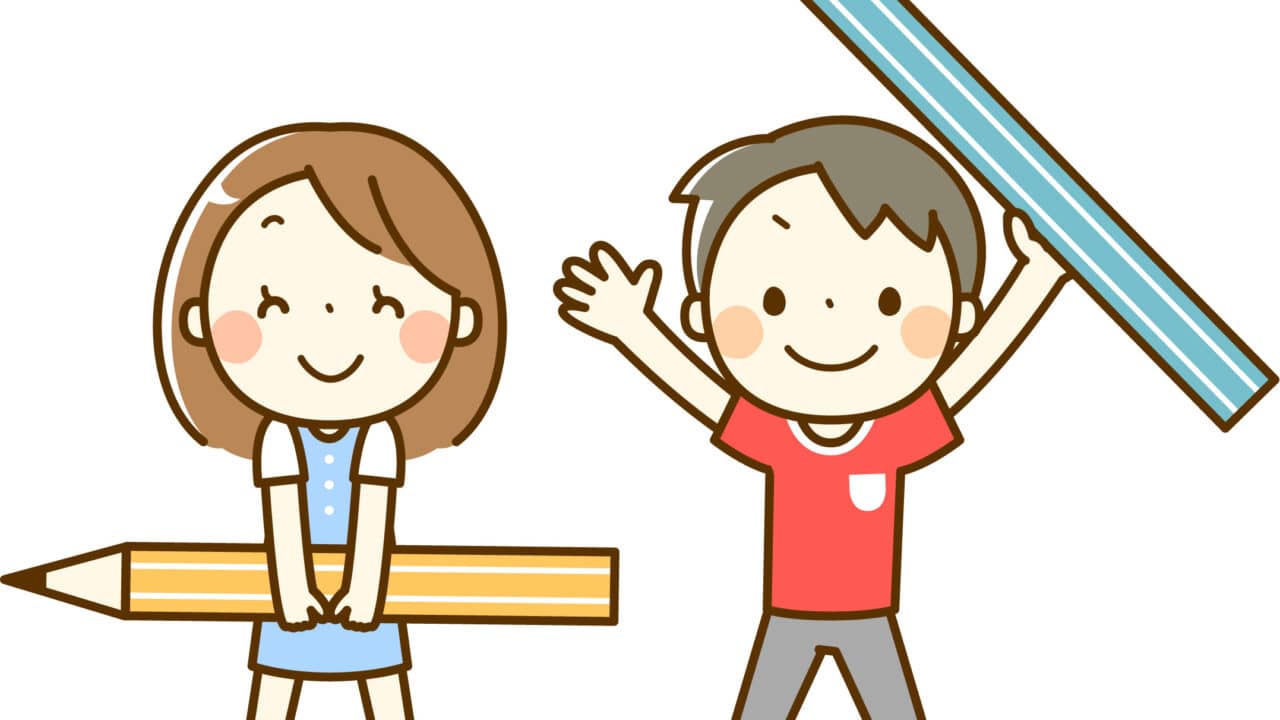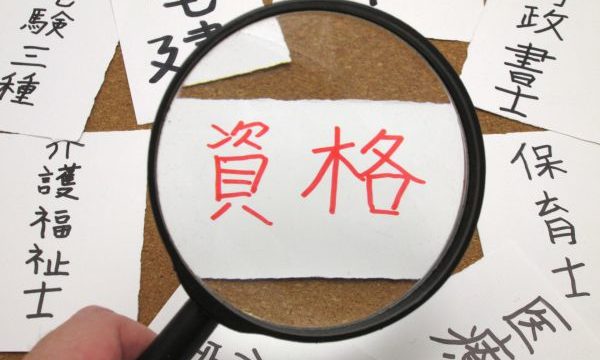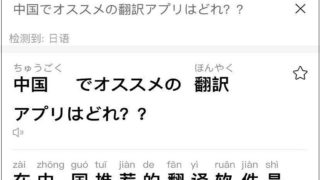こんにちは、『シンパパ』こと、ふみふみです。
ツイッターでは一部の方々からシンパパさんと呼ばれ親しまれて(?)おります(笑)
この記事を見ている方は、子供が勉強しない事に関して悩まれてる親御さんの方々かな~と思います。で、率直に言います。
今のあなたの状態で、『おらぁ!ちゃんと子供に勉強させやんかいやゴルァ!!٩(╬ఠ༬ఠ)و!!!』って誰かに言われて、素直に『あ、そっか!もっとちゃんとしよっ!!』って前向きになれますか??
かつ、それを毎日言い続けられる事で子育ては順調になりやがて問題は無くなると思いますか?
いやいや、無理ってもんでしょう・・・。子供にも同じ事が言えると思います。今のあなたが求めているのは、どっちかと言うと、わからん(納得いかん)事に対して、『困ったな~~、どうしたら出来んのかな~~』って、一緒になって誰かに考えてほしい、って事ちゃいますか?(←自分に言ってるw)
子供だって、学校や色々な人からの情報で、ちゃんと勉強した方が良い事や、頑張らないといけないなんてことは少なくとも理解しています。怒って勉強をさせる事はその瞬間は効果があるかもしれませんが、その一瞬で終わります。(で、さらに勉強嫌いになるというスパイラル・・・)
親に必要なのは、わかっていても出来ないもどかしさ、面倒くさいが勝ってしまうという子供の心理に少しでも寄り添って、少しずつでも頑張るきっかけを作る、時には一緒に困り、考え、共感し、親子の信頼関係を築いて、無理なく『そろそろ勉強しょっかな~』って感じになれる環境作り、というのが一番大切なんちゃうかと思います。
子供が言う事を聞かない・勉強しない
ここでは我が家あるあるの”子供が言う事を聞かない”という事について触れます。そもそも、子供は言う事を聞かないものです。勉強も最初から好きな子なんていません。(勉強を理解する事に楽しさを覚えて、勉強好きになる子は少ないですがいてると思います。)
だいたいの子供(中学生以下)が勉強をする理由は以下だそうです。
親から言われるから(真面目さ)
競争心
周りがやるから
自己顕示欲
上記を見る限り、親の声掛けもさながら、子育てにとって周りの環境(友達関係等)がとても大切だという事になります。とはいえ、最初から勉強が好きで好きでたまらない!なんて子供はいてないわけですね。私の場合は、『なんでうちの子はこんなに勉強が嫌いで、言う事も聞かないんだろう・・・』なんて悩みは捨ててしまう事としました。
人は急には変わらないからです。急激な変化を求めてはいけないという事をまずはしっかりと意識しましょう。(そうせんと身が持たんのです・・・)
問題無く学校に通えている事が前提ですが、勉強が必要というインプット(刺激)は子供に伝わっているはずです。そのうえで、少しずつ、少しずつ、勉強にも興味を持てるように仕向ける事が重要です。勉強って、理解出来たら楽しいやん!とかってなってくれた日には、しめたもんです。具体的な方法について順を追って書いてゆきます。
どうすれば子供が自分から勉強するようになるのか?
どうすれば子供が自ら勉強するようになるのか・・・?このテーマは果てしなく自分の中で議論を繰り広げた内容でもあります。ヒントは息子との会話の中から見つけたような気がしています。
息子『わくわくする事が有れば勉強を頑張ることが出来る』
わくわくか・・・。
自分から勉強をする子供にするために必要な事は、『わくわくさせる事』だと考えます。
で、具体的には、やはりご褒美を用意するという事が効果が高いように思います。(他にもあるかもしれませんが)
例えば、今はやりのスマホやゲームやネット動画、無料の物から有料の物までたくさんありますが、私(小5)の娘の場合任天堂switchのスプラトゥーン3が欲しい、息子(中三)の場合宇宙戦艦ヤマトの2203シリーズが見たい、等の要求をしてきた際に、今後の勉強に対する目標やルールを紙に書けるなら買って(見せて)あげる、というようにしました。
すると、自然と決めたことはやるようになってきましたし、渋っているときも、約束したでしょ?って言えるから言いやすいです。
※その時の目標は、あくまで少し頑張れば手が届く、実施可能な物である必要が有ります。高すぎる目標を立て、途中であきらめてもーたら元も子も無いからです。ハードルは少しずつ上げていき、頑張ったらわくわくする事が出来るぜって事を少しずつ刷り込んでいきましょう。
私の場合はこんな感じです。
娘
↓前回の通知表
国語=〇
算数=〇 その他割愛
↓目標
国語か算数どちらかの教科で◎を取る
息子
夏休み前に勉強がわからない事で学校行くのいやいや病になった
↓
上記記載した方法で1日1~2時間勉強をする事で何とかついて行けるようになった
↓目標
今の頑張りを継続して、テストの順位をこれ以上落とさない(今の順位以上を死守する)
目標は、宿題を〇〇時までに終わらせる、等でも良いと思うんですが、それだと答えを移すと簡単にごまかせてしまえるため、あくまで第三者からの評価をメインの目標にしてみました。
普段から、その子が何が好きで、何に価値を感じているのかにアンテナを立て温かく見守ってあげましょう、で、面白そうな情報が有れば、教えてあげる、こんなのもあるみたいよ?って感じです。
で、子供から何か要求してきたときにはしめたもん。勉強との結びつけ(約束)をあくまで手の届く範囲内で行い、それを守らせる、かつ、この方法を繰り返す、という事になります。
好きな事、わくわくする事から勉強に繋げる事で、『継続性のある勉強する理由』を作ることが出来るのだと私は思います。特に、小さいうちは、将来のため=勉強する!とスムーズにつながる子ってのは非常にまれだと思うので、そういう意味でもご褒美は必要悪のように感じますね。
あと補足ですが、少し前に、息子が、『命令されるとやる気がなくなる』とか、『”終わってんのか?”って言われたら”宿題全部完了したのか?”に聞こえる』とかって言ってた事からも、我が家の子供に対しての声掛けは命令形ではなく『進んでるかい?』や『いつやるか考えてる?』という進捗確認系で、また、子供が自分から勉強の事をやりだしたり、言い出したりしたら、ここぞとばかりに褒めちぎる(←あまり派手すぎると不自然がられる)。という事を我が家では継続するようにしています。
子供に『勉強しなさい!』と怒ること
言う事を聞かない子供、勉強せずゲームや好きな事ばかりする子供、見てるとイライラしますよね・・・。
うちもそうです。例外は有りますが、ほっといたらほぼ好きな事しかしてない印象が非常に強いです。
『勉強しろ!!』と怒りたくなるのは仕方ない事だと思います。
しかしながら、怒る事でその日勉強する事が出来たとして、それで得られる成果はその1回で終わります。それに対し、『怒られて勉強をやらされた』という嫌な想い出は子供の心にずっと残ってしまい、勉強嫌いの子供に育ってしまう可能性が高くなります。
生存本能、という話に戻るのですが、『恐怖』に対し生物が持っている対抗手段は主には2つで、①戦って勝利する または ②逃げる、という事になります。
怒られるという恐怖に対し、①戦う(勉強する)という選択を取らせることはその瞬間は効果があるかもしれませんが、勉強嫌いな子供にしてしまう可能性が高いうえに、下手をすれば②逃げ出す、という事にもなりかねません。
どちらかというと、”恐怖”という”生存本能”から”勉強”に繋げるのではなく、”わくわく”という”生存本能”から”勉強”に繋げてあげるほうが、継続性も中身も有るとても有意義なものになる事と思います。
事実、息子の学校のカウンセラーさんからも、『いかに親が子供に対し(勉強しなさいと言った)直接的な働きかけをしたからと言って、なんとかなったというケースは見たことが無い』との事でした。
もちろん、ただ忘れているだけ、という事も有るので、定期的な声掛けは必要ですが、あくまでそれは命令ではなく、進捗確認程度にとどめ、出来たことに対してはしっかりと褒めてあげるように、我が家では注意しています。
思春期(反抗期)の子供に『親が言って聞かせて』素直に勉強させる方法は?
これはまさに誰もが知りたいテーマになると思います。
私も実際に子育てカウンセラーさんにこの質問をしたことが有りますが、その結果も踏まえた結論は、『不可能!』です。
ただでさえ普通の事が不通に出来ない反抗期・・・。親から“言われて”素直に勉強なんて、そんな事出来るはずが有りません。
それに、諦めるとまではいきませんが、『そっか(笑)、不可能なんか~(笑)』って割り切ってしまうと、なんだかちょっと気が楽になりません??(笑)
とはいえ、学校の先生や、周りの大人・友達から言われた事であれば、心に響く可能性があるかもしれません。生活環境や、普段の行動に出来るだけ気を使い、出来るだけ子供の心に寄り添い、親子の無駄な衝突は避けるようにした方が無難と思います。(お互いに疲弊します。)
普段から子供とどのように接するべきなのか
子供と一緒に生活をしていく中で、親がどのように接してあげるか?という事について思う事を書きます。
子供とのぶつかり合いや、意見の衝突、『何でそんなことも出来ないの?』と感じるような事、有りますよね。
今まで私が子供と接したり、色々なところから得た情報で感じている事としては、いかに子供に対し一方的に意見を主張しても、子供の心には響かない、という事です。心に響かなければ、どんなコミュニケーションも意味を成しません。
大人でもそうですが、例えば仕事で嫌いな上司からグダグダと説教をされたとして、その後何かを変えようと感じるでしょうか?大人であれば多少の例外はあるかもしれませんが、相手が子供となると、ほとんどの場合あまりプラスに働かない事が多いと思います。
それでは、プラスに働く時ってどんな時でしょうか?
それは、子供が自分からその事柄に対し価値を感じた時、だと思います。
例えば、勉強を頑張っていい学校に行きたい、だったり、テストの点数が良かったからお母さんが喜んでおいしいものを食べに連れて行ってくれた、だったり、それは子供により様々です。
ですが、そこが一番難しいポイントでもあると思います。子供は千差万別、1万人いればみんな違います。何が言いたいかというと、何がきっかけになるかはその子次第のため、どの書籍にも書かれていない、分からないという事です。そのため、親が常に普段から目を光らせ、その子が何に興味を持っているのか、何をすれば喜ぶのか、何をされると嫌がるのかという事を見極める事がまず必要になります。
そのために一番重要なのは、親と子供の信頼関係です。信頼関係が悪いと、子供は考えを親に話さなくなります。そうなると、打てる手立てが少なくなってしまいます。子供の意見を無視した一方的な意見の主張(グダグダと説教する事)は、信頼関係を悪くしてしまううえ、プラスに働く事は少ないと思いますので、極力避ける方が良いと思います。
子供がプラスに転じるひらめきをするきっかけは、親が直接的に気付かせてあげられる事も有るかもしれませんが、子供が家の外で体験した事の中にヒントが有る可能性も有り、それは年齢を重ねていけばいくほど可能性は上がると思います。
そのため、親がしてあげられる事としては、子供が考えている事に同意・共感し、それを言葉にして表現(言語化)してあげる、という事です。
〇〇が壊れてしまって悲しい、とか、〇〇が達成できてうれしい、とかの時に、『一生懸命作ったのに壊れてしまって悲しいね』とか、『今までいっぱい頑張ってきたから、出来たね、お父さんもとても嬉しいよ、頑張って出来た事だと、とてもうれしくなるね』とかでしょうか。(もっと良い言い方が有るかもしれません)
子供は大人に比べ、この言語化の能力がそれほど高くなく、気持ちを表現する手段が大人より圧倒的に少ないです。子供が外から何か情報を得られる場面に遭遇した時に、この言語化の能力が少しでも高い方が、より質のいい情報を得られる可能性が上がります、また、親が同意・共感してあげる事で、子供との信頼関係も上がります。
思ってることを思ってる通りに人に伝えるって事が上手になると、外で興味のあることに出会ったときに食らいついていく、追及できる選択肢も増えます。そこから自分の将来に対して興味を持てることだってあるかもしれません。
長くなりましたが、これらの事が理由で、普段からの子供との接し方として重要な事は、親が子供の気持ちと同調し、認め、共感し、それらを言語化する手助けをする、という事だと私は思います。
そうする事で、子供が自らを表現する方法を知り、興味のある事をより追及する可能性を上げる事が出来ます。結果、自分にとって本当に必要なことに価値を感じられる可能性も上がると思います。
もちろん、ぶつかり合いが有ってはならないという事ではありません。同意・共感が有る前提でぶつかり合うのであれば、それはおおいに必要な事と思います。
これが私が経験してきた中で、今のところ重要と思える内容となります。
最後に
子供が言う事を聞かない、自分から勉強しない時に効果のある特効薬のようなものは、存在しないと思います。普段からの習慣や親からの働きかけにより、少しずつ培っていくものだと考えます。それが、子育てという事でしょう。
もう疲れた・・・。と感じてしまうのは、『理想通りになっていない』と感じているからです。時には、理想を下げてしまうという事も必要なのだと思います。妻を亡くした私が今感じている事は、人生において、『生きる事』以外に、MUSTな事なんてありません。それ以外は全てBetterです。『〇〇出来たら良いよね~』程度に考え、気楽にいけばいいのではないでしょうか。
怒鳴りつけてやらせると言う事は確かにその1回だけは効果があるかもしれませんが、しかしそれは『やるべきことに対する嫌悪感』となり、その子の将来にとって悪影響を長期にわたり与えてしまうと思います。
まず第一は子供との信頼関係、これが無いと話が始まりません。そのうえで、子供が自分から勉強ややるべき事をしたいと思える環境をいかに作ってあげるか、これが親に出来る子供への最大のプレゼントだと私は考えています。
そして、子供に対して見返りは求めない。親は子に、子は更にそのまた子に、親の愛はそうやって引き継がれていくもののような気がしています。
という事で、今日の執筆はここまでとさせて頂こうと思います。
続きはまた気が向いたら書きます!最後までお読みいただいた方がもしいらっしゃったとしたら、心からお礼を申し上げます。有難うございました。
プロフィール
2020年7月に妻を亡くしてから、男手1つで中学2年の長男、小学4年の長女を育ててきました。最初はさすがに絶望の海、不安しかない状態から3人の生活が始まりましたが、最近は少しずつ落ち着いてきて、随分とはいかないまでも片手間でブログ記事を更新する時間くらいは出来てきました。
そんな中でこれまでの体験を元に分かってきた我が家の子供たちの生態をここに書き記そうと思います。どなたかの参考にして頂ければ幸いです。
※この記事の内容は、一部、息子の中学校(私立)のカウンセラーさんから教えて頂いた内容等を含めております。
↓これ、ポチって頂けますと、とてもうれしいです。